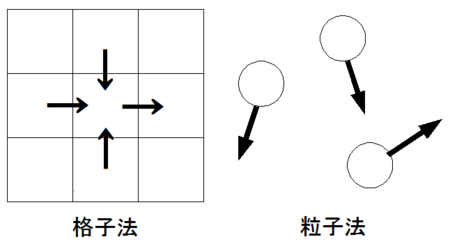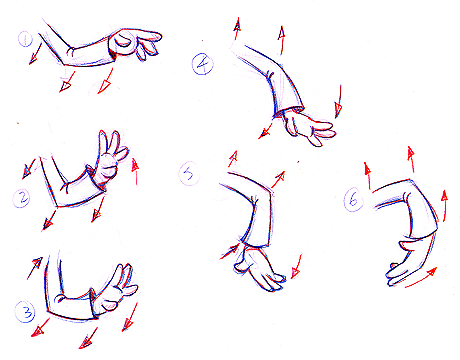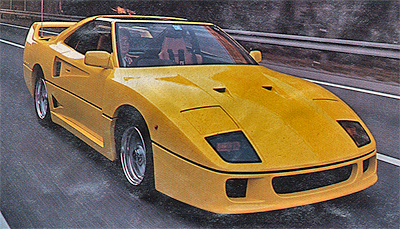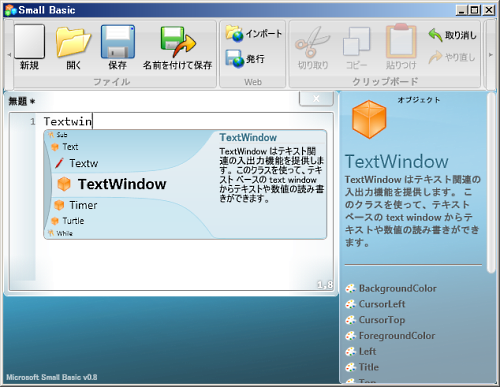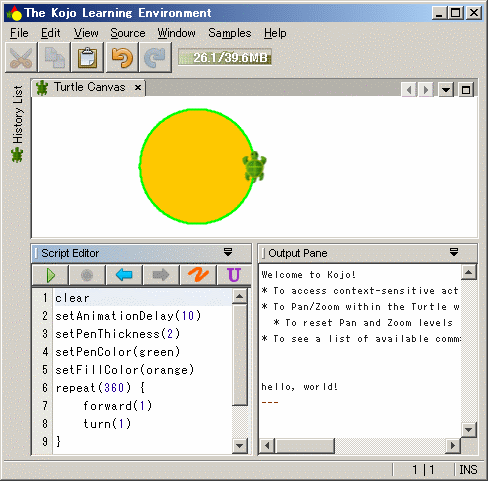水蒸気(すいじょうき、Water vapor、Steam)は、水が気化した蒸気。
特に、沸点以上における水の気体状態を指すこともある(→過熱水蒸気、臨界状態は除く)。
ただし沸点以下でも水は気体として存在でき、常圧において沸点以下の温度でも水は空気中にある一定量まで気化している(→蒸気圧、飽和水蒸気量)。空気中の水蒸気量、特に飽和水蒸気量に対する水蒸気量の割合を湿度という。
小学生の学習Q&A(Benesse教育情報サイト)
「湯気」と「水蒸気」は同じものではありません。水が沸騰しているやかんの口を、よく観察してみてください。口から少し離れたところで白い煙のようなものが出ているのがわかると思います。これが「湯気」で、やかんの口と「湯気」の間にある見えない気体が「水蒸気」です。

沸騰した水は、まず目に見えない気体の「水蒸気」となって口から吹き出し、熱い水蒸気がまわりの空気に触れて冷やされ、目に見える細かい水滴になったものが「湯気」となります。
気体の状態では、空気のように人間の目には見えません。目に見えるときは、それは気体ではなく「液体」、つまり湯気なのです。
※やかんを観察するときは、顔の近づけすぎにご注意ください。
湿度:飽和水蒸気量、露点
飽和水蒸気量
水蒸気は水の気体の状態で、目に見えません。
しかし、空気中にふくまれている水蒸気の量のちがいで、わたしたちは「空気が乾いている」とか「空気が湿っている」などと感じています。
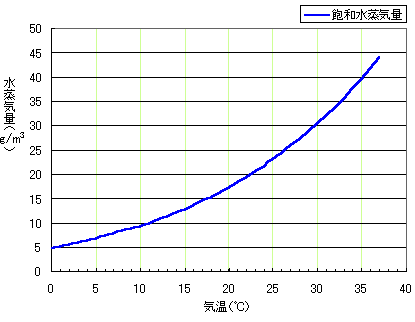 | 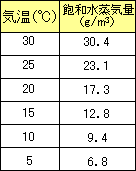 |
これ以上水蒸気をふくめない状態(水蒸気が飽和の状態)になったときの空気の温度を「露点」といいます。
そのときの空気の露点は、そのときの水蒸気量によって決まります。(気温で決まるわけではありません)
飽和水蒸気量
飽和水蒸気量は、温度とともに変化します。たとえば10度の空気1立方メートルには、最大9.4gまでの水蒸気しか入ることはできませんが、20度の空気1立方メートルには最大17.3gまでの水蒸気が入ることができます。
湿度: Wikipedia
湿度(しつど、humidity)とは、大気中に含まれる水蒸気の量や割合のこと。数種類あるが、通常は相対湿度を意味する。
-------------
個人メモ:
水蒸気というと一般的に湯気と混同されている。水蒸気は目に見えない。
水蒸気は100度(沸点)以下でも(温度が低くても) 空気中に存在している。(湿度として感じる)
目に見える物は湯気
温度が低ければ低いほど湯気は発生しやすくなる。
蒸気機関などから噴出して、目に見えているのは・・・
1)温度の高い内部から温度が低い空間へ水蒸気が放出され、
2)飽和水蒸気量が低くなるために、水蒸気として存在できない。
3)水蒸気が湯気(液体:水の粒)に変わる。(冷たい窓に結露するのと同じ)
4)この湯気が目に見える。
5)噴出するときは内部圧力が高く外部へ放出されるので、粒子の動きは維持している。
そのため、外へ吹き出す動きがある。
6)外へ吹き出すと共に圧力がさがり、動きのエネルギーを失い、
7)大気中の空気の流れから影響をうけはじめる。
8)それと同時に湯気となっている。
湯気が白く見えるのはなぜか?(Yahoo知恵袋の解答)
湯気は、液体です。非常に小さな微粒子状の液体です。水蒸気は目に見えません。
なぜ、見えないか、それは、水分子1個を肉眼で見ることができないからで す。
見えたら、顕微鏡で分子が見えると言うことですからね。
液体になると、かなりの水分子が集まっているので、光を乱反射して、白く見えます。
白いのは、 乱反射の結果です。例えば、氷は透明ですよね。
でもかき氷にすると白くなります。あれは、結晶の面が不規則な方向に並んでいるため、光が乱反射するからで す。湯気も同じ事です。
ヤカンから上がる湯気は、部屋の湿度が上がり続け温度も上がり続けると、発生する湯気の量も減る。
反対に、冬の室外は温度が低いため、でヤカンから上がる湯気の量は、室内よりも多い。
湯気の消滅:
9)温度が下がり湯気となったのだが、視界がクリアな空間は飽和水蒸気量に達していない。
10)そのため小さな水の粒である湯気は、温度が低い状態で再度蒸気に変わる
11)すなわち乾燥する。
12)湯気となった水の粒は、空気中で拡散(Wikipedia)する運動もそれに加わっている。
13)そのため広がりながら消失するように見える。
煙との違い:(Yahoo質問箱:湯気はどこへ消えるのでしょうか?)
煙は拡散です。風のないとき(多少あっても)なかなか消えません。
気流が安定していると、長く尾を引いてたなびきます。
気流が乱れると速く拡散し、小さい粒一つが識別できない間隔に拡散すると見えなくなります。
気流が乱れると速く拡散し、小さい粒一つが識別できない間隔に拡散すると見えなくなります。
人間の目の分解能は煙粒子一粒を見分けられるほど高くはありません。
湯気の拡散ももちろんあるでしょうが、見えなくなるまでの時間が全然違います。
微細粒子の拡散で、識別不能になる時間と、微小水滴が蒸発しながら拡散するのでは、あきらかに蒸発する方が早く見えなくなります。粒子の大きさにもよるでしょうが、煙粒子は、最後は落ちてくるものです。
※「水は沸騰して湯気になる」という考えにとらわれると、温度の高いとき(100度)しか湯気にならないとかんがえてしまう。
※「乾燥」の実験や観察は長い時間コップに入れた水の減少で確認することが多いので時間がかかると考えがちだが、そうではない。
参照:(Yahoo知恵袋)
なぜ気温が高いと冷凍庫など冷たいものから湯気がでて又気温が低いとお湯から湯気が出るのでしょうか?
>なぜ気温が高いと冷凍庫など冷たいものから湯気がでて
これは発想が逆です。
室温が冷凍庫の冷気に冷やされて気温が下がります。
気温が下がると、これまで水蒸気として空気中に存在していた水が凝縮して
液体(霧)になったのです。
気温が下がると、これまで水蒸気として空気中に存在していた水が凝縮して
液体(霧)になったのです。
※ この場合、流体の動きは冷気の動きであり、湯気となったのは空気中の水蒸気
>気温が低いとお湯から湯気が出る
お湯付近では気温が高いく、湿度はほぼ100%でしょう。
それが室温まで冷やされるとやはり飽和水蒸気量が下がりますから
水蒸気が凝縮して液体(湯気)になったのです。
※この場合、流体の動きは温度の高い空気の動きであり、湯気はその空気に含まれる水蒸気
>あと具体的に~度温度差があると湯気が発生するとかあるんでしょうか?
以上のことからわかったと思いますが、温度差だけでは決まりません。
湿度+温度の条件が必要で、
空気中の水蒸気量>その温度での飽和水蒸気量
という条件で湯気(霧)が発生します。
※ 温度が低くても二つの空気内で温度差が生じればそこに湯気が発生する。
空気が冷やされると飽和水蒸気量が小さくなり、それ以上水蒸気として維持できなくなる。
鍵となるのは「冷やされる」ということ。
気温-45度でお湯をまく動画
-------------
靄(もや):Wikipedia
靄(もや/Mist)とは、霧と同様に空気中の水蒸気が凝結して細かい水滴となり浮かんでいて視程が妨げられている状態であるが、霧よりも薄いものをいう。
日本式の分類では視程が1km未満のものが霧、1km以上10km未満のものが靄である。
霧(きり):Wikipedia
霧(きり、英称:Fog) とは、水蒸気を含んだ大気の温度が何らかの理由で下がり露点温度に達した際に、含まれていた水蒸気が小さな水粒となって空中に浮かんだ状態。
水粒は雨粒に比べて非常に小さいが、通常、根本的な霧の発生の原因は大気中の水分が飽和状態に達したものなので雲と同じであると考えてよい。
雲と霧の一番大きな違いは水滴の大きさなどではなく、両者の定義の違いである。すなわち、大気中に浮かんでいて、地面に接していないものを雲と定義し、それが地面に接しているものを霧と定義する。例えば、山に雲がかかっているとき、地上にいる人からはそれは雲だが、実際雲がかかっている部分にいる人からは霧なのである。なお、山の地面に接する霧または雲のことをガスと呼ぶことがある。
層雲:Wikipedia
層雲(そううん)は雲の一種。最も低い所に浮かび、灰色または白色で、層状あるいは霧状の雲のこと。輪郭はぼやけていて、厚みや色は一様であることが多いが、ちぎれて独特の形になる場合もある。霧雲とも呼ばれ、霧をもたらす雲の代表格である。
基本雲形(十種雲形)の一つ。ラテン語学術名Stratus(ストラタス)は、ラテン語の動詞 sternere (拡張する、広がる、平らにならす、層で覆うなどの意)の過去分詞 stratus に由来する。略号はSt。
海や川・湖などの暖かい水面上に冷たい空気がやってきたとき、冷たい水面や放射冷却で冷えた陸上に暖かく湿った空気がやってきたとき、山沿いに湿った空気が上昇して空気が冷やされたときなどに発生する。また、雨が上がった直後などに、地上付近や山の山腹・頂上付近、上空低いところなどに残るちぎれ雲も層雲である。山から立ち上るような雲の場合は、山旗雲(やまはたぐも)と呼ぶこともあるほか、地域的な名称もある。